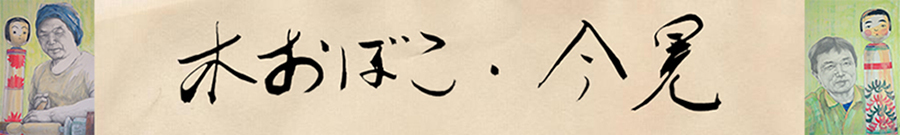今さんは、昭和56年9月、鳴子こけし祭り終了後、岡崎斉司さんの元を弟子上がりして、弘前に戻ってきました。そして、同年の冬から本田功さん、長谷川健三さんとともに、「ねぷたの館」に隣接した「こけしの館」で働き始めました。
初め(館時代)は、こけしを作らず、独楽などの木地玩具だけを作っていました。本田さんに勧められて、帰弘して、初めて(昭和56年11月)作られた鳴子型こけし(「B025」)下の写真1は、今さんが木地挽きをし、面描やモミジの胴模様は本田功さんが描かれた。
昭和57年1月下旬からこけしを作り始め、「おおき」などにて販売をされた。今さんにおかれては、「伝統型や本人型こけしの胴模様を今晃としてどのように描くか!」と模索をされていた時期でした。その試作品には署名のないもの、販売をする気もない習作期のこけしが工房にあったようで、清俊夫さんや桑原金作さんらは訪問時に分けてもらっていたようです。
上写真左から、「B013」(模様は不明)、「B039」(下の写真2には胴の裏表に描彩練習をされています。)、「B030」(椿模様)などは、昭和57年館時代の作です。伊太郎型の「B031」と「B038」は昭和57年11月作で、胴模様の模索時代の作であり、「B031」署名はされていません。
図譜「木おぼこ・今晃」の「B鳴子・館時代」「C禰宜町時代」初期作には、その変遷、模索作のこけし群が掲載されています。そして、嶽開拓地へ移住され、意欲的に、創作された本人型こけしへと昇華して行ったようです。